美味極楽メインページ > 魚の国ニッポンを釣る! > 【特別編】東京湾の未来を考える|東京湾を舌で感じる
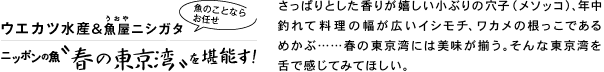
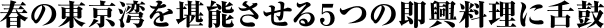


三枚に下ろした塩イシモチは、腹骨と血合い骨を取って金串に刺す。皮面を直火で焼いたら、素早く冷水に取る。水気を拭き取り、刺し身に切る。これが、塩イシモチの火取り。
春の魚には、菜の花がよく似合う。薬味はワサビよりも、やっぱり生姜。捨てがたい辛子醤油も、お試しあれ。
U「年中釣れるイシモチだが、春は一味違うようだ。季節を食ってる感じだよ」

東京湾を見下ろす房総半島は、花の産地だ。関東ではいち早く、春が訪れる。
ワカメの根っこ部分は胞子をつくる胞子葉で、一般にメカブ(芽株)と呼ばれる。東京湾では10月下旬頃、胞子を細ロープに移植して海中の棚に張る。
12月には柔らかい一番ワカメが採取され、年を越すと2メートルにも成長する。高級ブランドになった『猿島ワカメ』のメカブが、手に入った。
K「おぉ〜、きれい!」
褐藻類であるワカメは茶褐色をしているが、湯を通した瞬間、鮮やかな緑色になる。そのメカブを、まな板の上で細かく叩く。すぐさま、納豆のように粘ってくるだろう。さらに叩いて鰹節と醤油を加え、かき混ぜる。このネバネバを、炊きたての飯に盛ればメカブ丼だ。
ワカメの根っこ部分は胞子をつくる胞子葉で、一般にメカブ(芽株)と呼ばれる。東京湾では10月下旬頃、胞子を細ロープに移植して海中の棚に張る。
12月には柔らかい一番ワカメが採取され、年を越すと2メートルにも成長する。高級ブランドになった『猿島ワカメ』のメカブが、手に入った。
K「おぉ〜、きれい!」
褐藻類であるワカメは茶褐色をしているが、湯を通した瞬間、鮮やかな緑色になる。そのメカブを、まな板の上で細かく叩く。すぐさま、納豆のように粘ってくるだろう。さらに叩いて鰹節と醤油を加え、かき混ぜる。このネバネバを、炊きたての飯に盛ればメカブ丼だ。
N「メソ(メソッコ=小型の穴子)はやっぱり煮穴子かねぇ」
U「なに言ってんのぉ、Nさん。メソこそ、白焼きでしょ」
穴子などウナギの仲間は、ヌメヌメとして掴みどころがない。彼らは粘液をウロコの代用として体を保護しているわけだが、ここに表皮粘液毒を持つ。血液にも弱毒が含まれ、生食には注意が必要だ。
U「Nさん、ワサビ。それと焼き海苔…」
N「えっ?」
U「メソと焼き海苔が、出会いのモンだってこと、証明してみようじゃありませんか」
いったんフライパンで酒蒸ししたメソッコの皮面が、キツネ色に焼けるとプクッと膨らんで焦げ目をつける。そこに、我が家とっておき、富津の焼き海苔が添えられた。皿に盛られた瞬間に、手が伸びてしまう。白焼きを海苔に包んでワサビ醤油で食べる味わいは、ふっくらの表現は妥当ではない。焼けていながら、清純に引き締まっている。噛みしめると穴子が潜む砂の残香だろうか、怪しげな甘みが口に広がる。それらをワサビの刺激と焼き海苔が上手く包み、のどへ通す。Nはたまらなくなり一升瓶の口を切る。
世間では天ぷら、煮穴子が主流だが、白焼きを食わずして穴子料理は語れない。それも、できることなら東京湾のメソッコだ。穴子は、生きているうちに処理せねばならない。目の前の捕れたてを誇った、江戸前の舌がここにある。
U「なに言ってんのぉ、Nさん。メソこそ、白焼きでしょ」
穴子などウナギの仲間は、ヌメヌメとして掴みどころがない。彼らは粘液をウロコの代用として体を保護しているわけだが、ここに表皮粘液毒を持つ。血液にも弱毒が含まれ、生食には注意が必要だ。
U「Nさん、ワサビ。それと焼き海苔…」
N「えっ?」
U「メソと焼き海苔が、出会いのモンだってこと、証明してみようじゃありませんか」
いったんフライパンで酒蒸ししたメソッコの皮面が、キツネ色に焼けるとプクッと膨らんで焦げ目をつける。そこに、我が家とっておき、富津の焼き海苔が添えられた。皿に盛られた瞬間に、手が伸びてしまう。白焼きを海苔に包んでワサビ醤油で食べる味わいは、ふっくらの表現は妥当ではない。焼けていながら、清純に引き締まっている。噛みしめると穴子が潜む砂の残香だろうか、怪しげな甘みが口に広がる。それらをワサビの刺激と焼き海苔が上手く包み、のどへ通す。Nはたまらなくなり一升瓶の口を切る。
世間では天ぷら、煮穴子が主流だが、白焼きを食わずして穴子料理は語れない。それも、できることなら東京湾のメソッコだ。穴子は、生きているうちに処理せねばならない。目の前の捕れたてを誇った、江戸前の舌がここにある。
魚に薄塩を当てておき、フライパンに湯を沸かしたら酒をほんの少し注ぐ。沸騰してから魚を入れ、沸騰手前に火加減して3分。長ネギを散らし、ポン酢ないし酢醤油をかければ完成。この料理、魚本来の味がごまかされることがない。
U「健康な魚は、下ごしらえさえしっかりすれば、これだけで旨い。酒が臭みを分解し、沸騰させないから旨みが逃げないわけだ」
味わうと、頷かずにはいられない。絶妙な火加減であるがゆえに、引き締まった白身は小気味よく骨離れして、噛みしめると魚の甘みが滲み出る。
N「イシモチ料理は、一般に塩焼き。オレは刺し身を好むが、煮魚もいいねぇ。水っぽいと言われる魚は、煮ても身が締まるんだ…発見したよ」
イシモチの名は、石持ちが語源。頭蓋骨に隠れる一対の耳石が、とても大きい。そんな発見も、この魚を食べる愉しみである。
U「5分でできる煮つけをやってみせようか。しかもこれ、調味料を計らなくてもいいのよ」
関東煮、という言葉がある。醤油とみりんで煮詰めた、甘辛味の煮魚のことだ。見た目は真っ黒な醤油色でありながら、食べるとほんのり甘い。伊豆では稲取のキンメの煮付けや、房総半島でも磯魚に同じような味付けをする。透き通った薄味で炊く関西風とは対照的だ。
全てのヒレをハサミで切り取り、腹ワタを出したら血合いを切って洗い、水気をしっかり拭き取る。スーパーで買って少し臭みがあるようなら、粗塩を擦り込むようにして全身を揉んで、酒を少量まぶし、再度流水で洗う。これで完全に魚の生臭さは解消するはずだ。
下ごしらえを終えたイシモチを大きくぶつ切り、半カップの酒を注いで中火にかけたフライパンに入れてフタをし、まず酒蒸しにする。3分ほどで火が通ったらフタを取り、醤油、みりんの順で適宜加えて甘辛にする。
あとは沸騰させながら、煮汁を魚にかけていくだけ。酒気で緩んだ細胞は、アッと言う間に煮汁を吸う。その間、5分で完成だ。焦げる寸前に火を止めてこそ、関東煮の真骨頂だ。
U「イシモチは最近でこそ魚屋に並ぶようになったが、鮮度の良いものは釣り人だけが知る魚であった。築地の衆でも、イシモチの刺し身が食いたくなると釣り宿に走ると言うよ」
N「もっと関東の食卓で、見直されていい魚だね」

西潟正人流
塩イシモチの火取り
塩イシモチの火取り
西潟正人流
メカブ丼
メカブ丼
上田勝彦流
メソッコの白焼き
メソッコの白焼き
上田勝彦流
イシモチの湯煮
イシモチの湯煮
上田勝彦流
イシモチの早煮
イシモチの早煮
詳しいレシピは次号から紹介いたします。

魚料理を“しくみ”で理解・実跡するための決定版。魚に対する知識と経験がギュッと詰まった1冊。これで魚料理は進化する。『ウエカツの目からウロコの魚料理』(東京書籍)1,500円。
 |
1953年新潟県生まれ。逗子市で地魚料理店「魚屋」を20年間営む。その後、東京新聞や日刊ゲンダイで連載の執筆や、TV旅チャンネル『漁師町ぶらり』のナビゲーターとして活躍。『釣魚料理図鑑I&II』(エンターブレイン)や『魚で酒菜』(小社)など著書多数。近著に『ウツボはわらう』(世界文化社)がある。
|