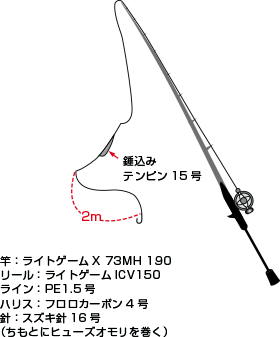美味極楽メインページ > 魚の国ニッポンを釣る! > 【最終回】初夏のスズキ[本牧]|スポーツ釣りとは違う


さて、我々が出かけたのは東京湾のスズキ釣りである。なんだスズキかよ、と言われるほどに、横文字でシーバスと気軽に呼ばれ、ルアーを駆使して陸からも船からも、釣れる時には十数本も釣れ盛る攻めの釣り、という印象が定着して久しいスズキ釣りであるが、そもそもこれほどにスズキが湾内全域に増えているのは、東京湾の埋め立てが進んでコンクリートの垂直護岸が増える中、そのような環境にこの魚の生態が適合したこと、そして、生息場所と季節によっては〝油臭い〟などと敬遠されて、釣って楽しむだけの、いわゆるキャッチ&リリースが普及したことによるものと推測される。
しかし。今回のエビによるスズキ釣りは、そんなレジャーやスポーツじみた釣りとは、いささか趣きが違う。いや、まったく違っていた。乗り合った神奈川県本牧港「長崎丸」は、この釣りの草分けで、現存する数少ない船宿だ。先が柔らかく胴のガッチリ固い竿と両軸受けリールを用い、細いPEを15号の鋳込み天秤につなぐ。その先には2.2メートルのハリス、そしてヒネリのない角セイゴを結び、チモトにはヒューズを巻きつける。その針を、同じ港の底曳網から分けてもらった10センチほどのサルエビの角の先に、水平の姿勢を保つよう、ちょいと刺す。
船を操る長崎功(いさお)船長は36歳3代目。その風貌の如く、まことに機敏に本牧の港周辺から猿島、沖の中の瀬にかけて巧みに船を操り、食い気のありそうな反応を探していく。ひとたび群れに当たったなら、釣り手は指示棚にピタリと忠実に錘の水深を合わせ、静かに魚信を待つのである。誘いといえば、時折エビが、ピン、と跳ね上がるような小さく鋭いしゃくりを入れればよい。水深と魚群の反応、潮の流れに応じた指示は、刻々と変わる。そう。釣り人のウデだけではない。「船長」と「船」と「釣り人」の三位が一体となって連動してこそ、この釣りは結果を出すことができるのであった。
スズキの大きな口と躯体を見れば、さぞかし暴食を想像するであろう。たしかにルアーにはガツガツと食いつくし、小魚を追っているスズキの食い気は見ているだけでも迫力がある。が、実際に岸壁などでウロウロと餌を探している平素のスズキを観察すると、この魚が実はエサ取りが下手であることがよくわかる。船長が説明するところによると、「スズキはアタッたと思っても、ヒレで叩いているだけのときもあるし、違和感があればすぐに吐き出すからね。最初の小さなアタリを見逃してはいけない」とのことなので納得だ。
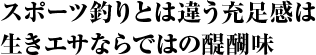

腰を落として竿をため、スズキと格闘するウエカツ。この手応え、大物か!?

成魚になったスズキは岸近くの潮通しの良い岩礁や磯に生息。東京湾では沖の瀬や、堤防まわり、河口付近がポイントに
さて。棚をとって構えると、船上には静かに緊張した空気が張り詰める。エンジンの音はもはや耳に届かない。釣り人は凪の海面に刺さった穂先を見つめ、時折スピーカーからの指示で我にかえって棚を取り直す。と、コン、と竿先が叩かれた?という感触。これがスズキのアタリなのだ。すかさず静かに1メートルほど糸を送り込み、一呼吸置いて、じわりと〝聞いて〟みる。〝もたれた…〟と見るやグイと合わせると、そこから先は大変なこととなる。細い道具に掛かったスズキは、雷鳴が轟くがごとく、逃れようと縦横無尽に突進し、東京湾を引っ掻き回すような大暴れを展開する。大きいヤツほど最初はおとなしいが、騙されてはいけない。それは大型ゆえの余裕であって、ご当人はまだ釣られたことに気づいていないだけだ。ヤラレタッと気づいたとたん、一気に炸裂する。のされないよう、何度も腰を落として竿をため、糸を送ってはかわし、魚が玉網に収められたところで一巻の幕となる。この間わずか数分なれど、その深さは悠久なり。静寂の戻ったデッキに、金色に縁取られた目を見張って息づくスズキを横たえた時、痺れる様な充足感が心身を満たす。
こんな釣りがあったとは…。独断的に、これを知らぬはもったいない、と申し上げておく。長崎屋の開業は昭和40年頃、かつて竹の手ばね竿で職漁師がやっていたこの技を、釣り人に知らしめた。現代に至り、道具や技術は進化したが、この釣りの原理原則は変わらない。温故知新。現代の江戸前釣りの結実がここにある。最近はルアーの流行に押されて客も減ったとはおっしゃるが、少なくとも釣りとしてのスズキ1本の価値が、まるで違う。ひとたびやったらルアーには戻れまい。「本牧は、昔はすごい漁場だったんだ」。赤銅色に日焼けた仲乗りの池田さんは、実は50年来の常連客。齢70越えにして船に誘われ、かくしゃくと語る。埋め立ての下敷きとなってなお、多くの〝根〟が魚たちを養っている。エビが獲れる5〜6月のひと月余りだけれど、在りし日の豊穣の東京湾をしのびつつ、初夏のスズキ釣りは「エビスズキ」にかぎる。
こんな釣りがあったとは…。独断的に、これを知らぬはもったいない、と申し上げておく。長崎屋の開業は昭和40年頃、かつて竹の手ばね竿で職漁師がやっていたこの技を、釣り人に知らしめた。現代に至り、道具や技術は進化したが、この釣りの原理原則は変わらない。温故知新。現代の江戸前釣りの結実がここにある。最近はルアーの流行に押されて客も減ったとはおっしゃるが、少なくとも釣りとしてのスズキ1本の価値が、まるで違う。ひとたびやったらルアーには戻れまい。「本牧は、昔はすごい漁場だったんだ」。赤銅色に日焼けた仲乗りの池田さんは、実は50年来の常連客。齢70越えにして船に誘われ、かくしゃくと語る。埋め立ての下敷きとなってなお、多くの〝根〟が魚たちを養っている。エビが獲れる5〜6月のひと月余りだけれど、在りし日の豊穣の東京湾をしのびつつ、初夏のスズキ釣りは「エビスズキ」にかぎる。
最近はルアーによる釣りが主流ですが、生きたエビで狙うスズキ釣りは、その昔、江戸前の釣りの中でも難しい釣りの一つとされていました。
それは、エビの針への刺し方はもちろん、特に重要で難しいのが魚の遊泳層にぴったりエサを漂わせること。長年の経験が必要なものだったのです。今は釣り船に魚群探知機があり、映し出された魚影の水深を正確に釣れば、はじめての人でも楽しめます。
そこで必須なのが船釣り専用のPEの道糸。10メートルごとの色分けに加え、1メートルごとにマークがあるので、正確に魚のいる水深にエサを届けることができます。また、小型のリールにも水深計が装備されたものが登場してきており、いっそう簡単に釣ることが可能になってきています。
あとは海に出かけるのみ。最初は難しいかもしれませんが、船長の指導に従って釣れば、ルアーにはない醍醐味、楽しさが待っています。
それは、エビの針への刺し方はもちろん、特に重要で難しいのが魚の遊泳層にぴったりエサを漂わせること。長年の経験が必要なものだったのです。今は釣り船に魚群探知機があり、映し出された魚影の水深を正確に釣れば、はじめての人でも楽しめます。
そこで必須なのが船釣り専用のPEの道糸。10メートルごとの色分けに加え、1メートルごとにマークがあるので、正確に魚のいる水深にエサを届けることができます。また、小型のリールにも水深計が装備されたものが登場してきており、いっそう簡単に釣ることが可能になってきています。
あとは海に出かけるのみ。最初は難しいかもしれませんが、船長の指導に従って釣れば、ルアーにはない醍醐味、楽しさが待っています。

沖釣りをライトにゲーム感覚で楽しめる竿「ライトゲームX 73HM-190」に、リールにはライトゲーム用の両軸「ライトゲームICV150」を使用。コンパクトなボディながら水深カウンターも装備しており、スズキの遊泳層に合わせるのも簡単。仕掛けを変えることでエサにもルアーにも対応できる。