美味極楽メインページ > 魚の国ニッポンを釣る! > 【第3回】東京湾 ハゼ・イイダコ|東京湾の恵み
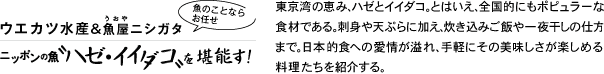
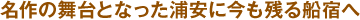
上田(以下U)「西潟(以下N)さんよぉ、東京湾が気になるんだよ。ハゼぇ釣りに、行かねぇか?イイダコも、ぼちぼち顔を見せてるみたいだし…」
水産庁でなくても、原発事故による魚介類への影響は大いに気にかかるところ。食いしん坊はなおさらだが、「浦安」という響きには、また違った感慨も湧いてくる。かの山本周五郎が大正15年の春から足かけ3年あまり千葉県浦安町に住み、『青べか物語』で回想しているからだ。
「浦安=青べか」と連想する世代は、もう古いような気がしないわけでもない。しかし、船宿が「吉野屋」と聞いて、心は動いた。作家が深く関わりをもった作中の釣り宿「千本」で、当時"長"と呼ばれていた小学三年生だった子孫に会えるかもしれない。
N「オレは今回も陸で待つ。浦安こそ、土地の取材が欠かせないのだ。では、幸運を祈る!」
大正8年に「江戸川放水路」ができると、かつての"本流"だった川は「旧・江戸川」になった。船宿はその際にあって、真上を地下鉄・東西線の鉄橋が架かかる。
U氏らを乗せた、釣り船「吉野屋丸」は鮮やかな緑色。川の流れにのって鉄橋をくぐり、東京湾へ向かって進んで行く。見送ってから気づくと、そこには浦安市教育委員会による『蒸気河岸』跡の立看板があった。
『このあたりは、かつて蒸気船「通運丸」の発着所があったところで、「蒸気河岸」と呼ばれていました。(中略)…東京方面への行商や通学には、この定期船が使われていました。(中略)…昭和17年に東京市営バス(通称青バス)が開通して…(中略)昭和19年に廃止されました』
山本周五郎が"蒸気河岸の先生"と呼ばれたのは、この近所に住んでいたからだ。彼がなけなしのカネで買った「青べか」を、「ぶっくれ舟」と嘲笑ったのが、先の「吉野屋」の"長"である。
「私が、"長"の倅です。あの写真に先生と一緒に写っているのが、オヤジですよ」と、船宿「吉野屋」のご主人、吉野眞太朗さん(62)は穏やかに笑う。壁には、セピア色になった写真がずらり。干潟が広がっていた時代の「脚立釣り」や、東京湾で絶滅したとされる「アオギス」の魚拓まである。夢を刷り込んだまま訪れる人も少なくないだろう。ご主人へのつまらない質問をよして、鉄橋下から東側へ伸びる「境川」に出てみた。昔は町の中心をなしていた"堀割り"は今、水門が閉ざされて淀んでいる。
『…(中略)洗い場にかがんで水中をすかして見た。黄昏の、片明かりに光る、水面の下をすかして見ると、青黒く藻草がゆらめいてい、なにかの稚魚が群れをなして、さっと片方へはしり、すぐまた片方へさっと走るのが見えた』
『青べか物語』の作中に描写される光景は、昭和に入ったばかりの頃だ。江戸川河口に広がっていた"沖の百万坪"や"大三角"と呼ばれた広大な干潟は、今「ディズニーランド」になっている。再び『蒸気河岸』跡に戻り、現実に帰ると、沖の釣果が気にかかる。
水産庁でなくても、原発事故による魚介類への影響は大いに気にかかるところ。食いしん坊はなおさらだが、「浦安」という響きには、また違った感慨も湧いてくる。かの山本周五郎が大正15年の春から足かけ3年あまり千葉県浦安町に住み、『青べか物語』で回想しているからだ。
「浦安=青べか」と連想する世代は、もう古いような気がしないわけでもない。しかし、船宿が「吉野屋」と聞いて、心は動いた。作家が深く関わりをもった作中の釣り宿「千本」で、当時"長"と呼ばれていた小学三年生だった子孫に会えるかもしれない。
N「オレは今回も陸で待つ。浦安こそ、土地の取材が欠かせないのだ。では、幸運を祈る!」
大正8年に「江戸川放水路」ができると、かつての"本流"だった川は「旧・江戸川」になった。船宿はその際にあって、真上を地下鉄・東西線の鉄橋が架かかる。
U氏らを乗せた、釣り船「吉野屋丸」は鮮やかな緑色。川の流れにのって鉄橋をくぐり、東京湾へ向かって進んで行く。見送ってから気づくと、そこには浦安市教育委員会による『蒸気河岸』跡の立看板があった。
『このあたりは、かつて蒸気船「通運丸」の発着所があったところで、「蒸気河岸」と呼ばれていました。(中略)…東京方面への行商や通学には、この定期船が使われていました。(中略)…昭和17年に東京市営バス(通称青バス)が開通して…(中略)昭和19年に廃止されました』
山本周五郎が"蒸気河岸の先生"と呼ばれたのは、この近所に住んでいたからだ。彼がなけなしのカネで買った「青べか」を、「ぶっくれ舟」と嘲笑ったのが、先の「吉野屋」の"長"である。
「私が、"長"の倅です。あの写真に先生と一緒に写っているのが、オヤジですよ」と、船宿「吉野屋」のご主人、吉野眞太朗さん(62)は穏やかに笑う。壁には、セピア色になった写真がずらり。干潟が広がっていた時代の「脚立釣り」や、東京湾で絶滅したとされる「アオギス」の魚拓まである。夢を刷り込んだまま訪れる人も少なくないだろう。ご主人へのつまらない質問をよして、鉄橋下から東側へ伸びる「境川」に出てみた。昔は町の中心をなしていた"堀割り"は今、水門が閉ざされて淀んでいる。
『…(中略)洗い場にかがんで水中をすかして見た。黄昏の、片明かりに光る、水面の下をすかして見ると、青黒く藻草がゆらめいてい、なにかの稚魚が群れをなして、さっと片方へはしり、すぐまた片方へさっと走るのが見えた』
『青べか物語』の作中に描写される光景は、昭和に入ったばかりの頃だ。江戸川河口に広がっていた"沖の百万坪"や"大三角"と呼ばれた広大な干潟は、今「ディズニーランド」になっている。再び『蒸気河岸』跡に戻り、現実に帰ると、沖の釣果が気にかかる。
大きなものは3枚におろして刺身に。小さなものは大量に集めて佃煮に。そして中型のもは、できれば干物にしてほしい。陰干しでじっくりと干しあげた干物を焼いて食べてもよいし、じっくり出汁を取ると、上品で香ばしい味わいの出汁に。雑煮の出汁をはじめ、味噌汁や蕎麦つゆなどに使っても旨い。また、行程の途中(5)までは、唐揚げにもつながるので、覚えておこう。

金製のザルにハゼを入れ、たっぷりの塩をまぶす。

ウロコを逆なでするように塩を揉み込む。ザルの編み目でウロコが取れる。

爪楊枝の先で肛門を突く。

ひっかかりを感じたら、爪楊枝をそっと抜く。長い腸がきれいに取れる。

塩、ウロコが残らないようにしっかりと水洗いする。

尾びれ手前に串を刺し、約1日陰干しすると干物のできあがり。
釣り上げたイイダコを船上で処理、海水で洗って、帰港するまでの間に潮風の中で生干しさせたのが本来の形。
これを漁師たちが「ひとっぽし」と呼んだそうだ。ひと晩干したら、焦がさないように軽く焼き上げ、手で引きちぎりながら食す。塩・胡椒で食べると、絶妙な味わいに。腹部を広げるための竹ヒゴの「輪っか」は、曲げる箇所を濡らしてから火であぶるとよい。

胴(頭部)に5ミリほどの突起物(ろう斗)がある側から指を入れる。

胴をめくると鉛色をした墨袋が見えるので、破らないように抜き取る。

墨袋と内臓を抜き取ったら胴を元に戻す。

ザルにイイダコを入れ、たっぷりの塩でしっかりと揉み、ヌメリを取る。

鍋に熱湯を沸かしたら、イイダコをさっと湯通しし、水洗いする。

水気を拭き取ったら、目玉と口を取り竹ひごを曲げた「輪っか」を胴に入れて、胴を広げる。

胴の先端部分に串を刺して干しておく。
 |
1953年新潟県生まれ。逗子市で地魚料理店「魚屋」を20年間営む。その後、東京新聞、日刊ゲンダイの連載執筆やTV旅チャンネル『漁師町ぶらり』のナビゲーターなどで活躍。また『釣魚料理図鑑I&II』(エンターブレイン社 刊)、『魚で酒菜』(小社 刊)など著書も多数。
|